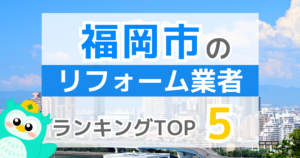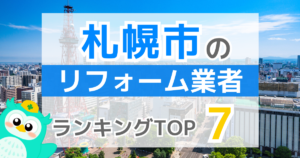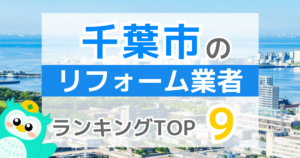リフォームする箇所を選ぶ
実家リフォームの費用相場と種類まとめ!活用しやすい補助金や減税制度も紹介

実家のリフォームを検討されている方の中には、下記のようなお悩みが生じるかと思います。
「実家のリフォームと建て替えだとどっちがいい?」
「実家をリフォームする際の費用相場はどれくらい?」
「利用できる補助金や減税制度はある?」
本記事では、実家のリフォームを検討している方に向けて、実家リフォームの費用相場や種類について解説していきます。
さらに活用しやすい補助金や減税制度も紹介するため、是非本記事を参考にしていただければ幸いです。
【関連記事】
>>リフォームの費用相場
市区町村を選ぶだけ
市区町村を選ぶだけ
目次
実家リフォームをする目的は3つ

まず最初に、実家リフォームをする3つの目的について紹介します。
- 安全性や快適性の向上
- 二世帯住宅への改装
- 家の継承・貸し出しのための価値向上
① 安全性や快適性の向上
実家をリフォームする目的の1つに「安全性や快適性の向上」があります。まず、快適性について考えてみましょう。
冬場の寒さや夏場の暑さは、住環境を悪化させ、健康に悪影響を与える可能性があります。そのため、実家のリフォームでは、断熱材の追加やエアコンの設置など、快適な温度環境を作ることが大切です。
次に、安全性の向上について考えてみましょう。
老朽化した電気配線やガス管は、事故や火災の原因になる可能性があります。そのため、実家のリフォームでは、電気配線やガス管の交換、手すりを設置するなど安全性を高めるための対策を講じることが大切です。
浴室やキッチンのリフォームなど、生活に必要な場所を快適に使えるようにすることも重要ですが、滑り止めの床材や手すりの設置など、安全面にも配慮することも大切です。
② 二世帯住宅への改装
実家をリフォームする目的の1つに「二世帯住宅への改装」があります。
二世帯住宅とは、2つの世帯が1つの住宅に住むことができるように改装された家のことです。
例えば、1つの住宅に2つのキッチンやバスルームを設置することで、2つの独立した住居が生まれます。壁を取り払って大きなリビングスペースを作ることも可能です。
二世帯住宅ならば、家族が一つ屋根の下で生活することになるため、より家族同士の交流を促進することにつながります。特に親が高齢の場合は、介護がしやすいというメリットもあります。
③ 家の継承・貸し出しのための価値向上
実家をリフォームすることで、「家の継承・貸し出しのための価値向上」が見込めます。家族や親戚が代々住み続ける家や、貸し出しをする予定の家は、将来的に価値が上がる可能性があります。
具体例として挙げられるのが「外装の改修」です。外壁の塗り替えや窓枠、屋根のリフォーム、エクステリアの設置など、家の外観が美しくなることで、周囲からの印象が良くなります。
これらのリフォームによって、家の継承や貸し出しにおいて、将来的に高値で取り引きできる可能性があります。将来的に売却する場合にも、高い評価を得ることができるかもしれません。
家族や親戚が代々住み続ける家を守るためにも、定期的なリフォームが必要不可欠です。
市区町村を選ぶだけ
市区町村を選ぶだけ
実家リフォームと建て替え どちらがいいか?

実家をリフォームを検討してる方の中には、建て替えにすべきか悩んでいる方も多いと思われます。
以下の表は、実家のリフォームと建て替えにおける、メリット・デメリットをまとめたものです。
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| リフォーム |
|
|
| 建て替え |
|
|
リフォームの場合、リフォームが必要な箇所のみ改修が可能であるため、建て替えよりも比較的費用を抑えることが可能です。
ただし、今の実家の土台は変えられないため、建て替えと比べると建物自体の強化は難しいというデメリットもあります。
建て替えの場合、間取りやデザインを大幅に変更できるため、今までの実家の間取りで不便していた箇所をほとんど解決できる可能性が高いです。
しかし、新築同様の工期や費用、さらに各種税金がかかるため、資金に余裕がないと難しいと言えます。
実家リフォームが向いている人
実家のリフォームが向いている人は、下記の通りです。
二世帯住宅へのリフォームを決めている人
住み慣れた家の面影を残したい人
費用や工期を抑えたい人
リフォームの場合は、実家を取り壊すことなく必要な場所のみを改修することができます。高齢の親にしてみれば、住み慣れた自宅で過ごしたいと希望することも多いため、二世帯住宅へのリフォームを検討している人に向いていると言えます。
建て替えが向いている人
建て替えが向いている人は、下記の通りです。
実家を引き継ぐ予定の人
間取りやデザインを大幅に変更したい人
断熱性や耐震性を大幅に見直したい人
建て替えの場合は、工期や費用が掛かる分、間取りやデザインを大幅に変更することができます。建物自体の耐久性も新築同様に戻せるケースもあるため、今後実家を引き継ぐ予定の人に向いていると言えます。
市区町村を選ぶだけ
市区町村を選ぶだけ
実家リフォームの種類と費用相場

実家のリフォームには、以下のような種類があります。
| リフォームの種類 | 費用相場 |
|---|---|
| バリアフリー化リフォーム | 5~30万円 |
| 断熱・耐震リフォーム | 断熱:350~550万円 耐震:100~150万円 |
| 内装リフォーム | 10~50万円 |
| 間取りの変更 | 10~70万円 |
| リノベーション | 1000万円~ |
| 外構・エクステリアリフォーム | 20~100万円 |
| 水回りのリフォーム | 10~150万円 |
| ヒートショックリフォーム | 10~80万円 |
リフォームの目的によってリフォームの種類が変わります。順に詳しく解説していきます。
バリアフリー化リフォーム
バリアフリー化リフォームは、住宅内の段差や障害物を解消することで、車椅子や杖などを使用する人でも安心して生活できるようにするためのリフォームです。
実家をリフォームするにあたり、高齢の両親が安心して過ごしたいと希望される方は多いです。身体状況によっては大幅な間取り変更をすることなく、両親が過ごしやすい空間にすることも可能です。
バリアフリー化リフォームの費用相場は、下記の通りです。
| 手すりの設置 | 1~3万円 |
|---|---|
| 段差の解消(出入口の敷居の取り替え) | 2~3万円 |
| 引き戸ドアへの変更 | 5~20万円 |
| 通路幅の拡張 | 30万円 |
なお、これらのバリアフリー化リフォームでは、介護保険を利用して在宅改修の費用の助成を受けることも可能です。
断熱・耐震リフォーム
屋根や床に断熱材を入れたり、外壁に断熱塗料を塗るといった断熱リフォームを行うことで、外気温の影響を減らして室内を保護することができます。
冬場は暖かく、夏場は涼しく保つことができるため、光熱費を節約することにもつながります。また、後に紹介するヒートショック対策にもなるため、高齢の両親のために実家の断熱リフォームを行いたいと希望される方は多いです。
断熱リフォームの費用相場は、下記の通りです。
| 壁の断熱施工 | 200〜300万円 |
|---|---|
| 天井の断熱施工 | 15〜90万円 |
| 屋根の断熱施工 | 40〜250万円 |
あわせて読みたい


非公開: 断熱リフォームの費用は?工事の効果や費用を安くする方法も解説!
「冷暖房が効きやすい部屋にしたい」「外気からの影響を少なくして快適な室温を保ちたい」という方は、断熱リフォームが適しています。ただ、断熱リフォームを費用面で諦めていませんか?この記事では、失敗しないために費用相場や補助金について詳しく解説しています。
「冷暖房が効きやすい部屋にしたい」「外気からの影響を少なくして快適な室温を保ちたい」という方は、断熱リフォームが適しています。ただ、断熱リフォームを費用面で諦めていませんか?この記事では、失敗しないために費用相場や補助金について詳しく解説しています。
地震の揺れを吸収する柱や梁の設置、壁の補強、地盤改良などを行う耐震補強リフォームにより、地震や自然災害が起きた際に実家や家族を守ることができます。
実家の場合、築年数が30年以上経っているなど耐震性が気になる方も多いと思われます。1981年以前の旧耐震性基準で建てられた住宅の場合、耐震補強リフォームはほぼ必須とも言えます。
耐震補強のリフォームの費用相場は下記の通りです。
| 外壁の補強(30坪) | 150万円 |
|---|---|
| 屋根の軽量化 | 100~150万円 |
| 柱の補強(耐震金物の設置) | 50万円程度 |
あわせて読みたい


非公開: 耐震リフォームの費用相場は?補助金制度や事例についても解説
自宅の耐震性を高める耐震リフォーム。ただ、費用面で挫折してしまったり、効果に疑問を感じてしまったりしていませんか?本記事では、耐震リフォームの費用相場や補助金制度といった情報まで幅広く紹介しています。耐震リフォームを検討されている方は、この記事を参考にしてみてください。
自宅の耐震性を高める耐震リフォーム。ただ、費用面で挫折してしまったり、効果に疑問を感じてしまったりしていませんか?本記事では、耐震リフォームの費用相場や補助金制度といった情報まで幅広く紹介しています。耐震リフォームを検討されている方は、この記事を参考にしてみてください。
市区町村を選ぶだけ
市区町村を選ぶだけ
内装リフォーム
内装のリフォームは住み心地が向上するだけでなく、リフォームによって空間がより自分好みにカスタマイズできるため、より快適な生活が送れるようになるでしょう。
実家の場合、内装や設備を十数年リフォームしていないご家庭も多いと思われます。クロスや床材の張り替え、建具の交換などを行うだけでも、同じ間取りなのに見違えるようにきれいになったと感じる方は多いです。
内装リフォームの費用相場は下記の通りです。
| 壁紙・クロスの張り替え(リビング) | 10~20万円 |
|---|---|
| 床材の張り替え(リビング) | 15~25万円 |
| 建具の交換 | 10~100万円 |
投稿が見つかりません。
間取り変更
間取り変更は、家の内部のレイアウトを改善するために行われます。
実家リフォームで多いのは、壁を取り払って大きなリビングスペースを作ることです。リビングスペースを広げるため、家族が一緒に過ごす時間が増え、家族の絆を深めることができます。
また、多世帯でも住みやすい住宅に変更するために、元々あった部屋を2部屋に分ける、和室を洋室にリフォームするケースも多いです。
間取り変更の費用相場は、以下の通りです。
| 1部屋を2部屋に分ける | 25~70万円 |
|---|---|
| リビングを広くする | 10~40万円 |
| 和室を洋室に変更する | 40~80万円 |
| クローゼット・収納の増設 | 10~20万円 |
あわせて読みたい


非公開: リフォームで間取り変更をする費用は?施工事例や注意点もご紹介!
本記事では、実際に間取り変更をした6つのリフォーム事例をご紹介しつつ、費用相場や注意点、リフォーム業者の選び方について解説します。理想の住まいをつくるための参考になれば幸いです。
本記事では、実際に間取り変更をした6つのリフォーム事例をご紹介しつつ、費用相場や注意点、リフォーム業者の選び方について解説します。理想の住まいをつくるための参考になれば幸いです。
市区町村を選ぶだけ
市区町村を選ぶだけ
リノベーション
リノベーションは、築年数などが古い建物を現代的な住空間に改修することを指します。建物全体を新築同様にするフルリノベーションは、建て替えよりは費用を抑えられることもあります。
築年数が古い実家の場合、天井や壁にクラックが入っていたり、フローリングが色あせたりしていることが多いです。天井や壁、フローリングの補修を行うことで、構造部分の補強が可能となります。
また、間取りや水回りを大幅に変更することで、実家を二世帯住宅にすることもできます。家族構成や生活スタイルに合わせてリフォーム内容を検討しましょう。
リノベーションの費用相場は以下の通りです。内容や規模によって費用は大きく異なります。
| フルリノベーション | 1,000~2,000万円 |
|---|---|
| 二世帯住宅化 | 500~1,200万円 |
あわせて読みたい


スケルトンリフォームとは?費用相場やメリット・デメリットも解説
中古マンションが市場に多く出回り、立地条件など揃った中古市場への期待感は年々高まりつつあります。そこで注目を集めているのが、間取り変更なども可能な「スケルトンリフォーム」というリフォーム手法です。本記事ではスケルトンリフォームの工法や、戸建てとマンションそれぞれの事例に基づいた予算の目安を中心に挙げていきます。
中古マンションが市場に多く出回り、立地条件など揃った中古市場への期待感は年々高まりつつあります。そこで注目を集めているのが、間取り変更なども可能な「スケルトンリフォーム」というリフォーム手法です。本記事ではスケルトンリフォームの工法や、戸建てとマンションそれぞれの事例に基づいた予算の目安を中心に挙げていきます。
外構・エクステリアリフォーム
外構・エクステリアリフォームは、建物の外観や庭などの外構を改修するリフォームです。
具体例としては、玄関や門扉周りの工事や庭の造園、駐車場の拡張などが挙げられます。エクステリアリフォームを行うことにより、実家の外観を新しく鮮やかにすることができます。
外構・エクステリアリフォームの費用相場は以下の通りです。
| 門扉・門柱の工事 | 15~30万円 |
|---|---|
| 庭の植栽 | 10~20万円 |
| 塀の増設 | 50~100万円 |
| ガレージの設置 | 100万円程度 |
市区町村を選ぶだけ
市区町村を選ぶだけ
水回りのリフォーム
水回りのリフォームは、キッチンや浴室などの水回りの設備を改装することを指します。設備の効率や安全性が高くなるため、生活の質の向上に繋がります。
実家をリフォームする場合、高齢の両親でも使いやすいように、ユニットバスや自動洗浄付きトイレへ交換される方は多いです。設備が古くなって劣化したり、使い勝手が悪くなってしまった際は水回りのリフォームを検討しましょう。
水回りのリフォームの費用相場は以下の通りです。なお、商品のグレードにより値段は変動するため、最低でもこれくらいは費用が掛かると見積もりましょう。
| キッチンの交換 | 60〜150万円 |
|---|---|
| お風呂の交換 | 80〜150万円 |
| トイレの交換 | 20〜30万円 |
| 洗面台の交換 | 10〜20万円 |
あわせて読みたい


水回りリフォーム3点・4点セットの費用相場は? 注意点や施工事例を解説!
キッチン、お風呂、洗面台、トイレが含まれる「水回り」は家の中でも特に消耗しやすく、不具合や劣化が起きやすい部分です。水回りリフォームを考える際にはリフォーム箇所別の費用相場を把握しておくことが重要です。この記事では、水回りリフォームの箇所別の費用相場や施工事例を詳しく紹介しています。
キッチン、お風呂、洗面台、トイレが含まれる「水回り」は家の中でも特に消耗しやすく、不具合や劣化が起きやすい部分です。水回りリフォームを考える際にはリフォーム箇所別の費用相場を把握しておくことが重要です。この記事では、水回りリフォームの箇所別の費用相場や施工事例を詳しく紹介しています。
ヒートショックリフォーム
ヒートショック対策は、急激な温度変化によって体調を崩すことを防ぐためのリフォームです。特に高齢者や生活習慣病を患っている方にとっては、必要不可欠なリフォームと言えます。
例えば、お風呂から上がって寒い脱衣所に出る時など、身体が急激な温度変化により血圧が大きく上下してしまい、ヒートショックを引き起こすことがあります。
そのため、床暖房や浴室暖房乾燥機の設置など、室内の寒暖差を小さくする対策が必要です。なお、前出の断熱リフォームもヒートショック対策に効果的です。
ヒートショック対策のリフォームにかかる費用相場は以下の通りです。
| 浴室暖房乾燥機の設置 | 10~30万円 |
|---|---|
| 床暖房の設置 | 50~100万円 |
| 内窓の設置 | 10~15万円 |
あわせて読みたい

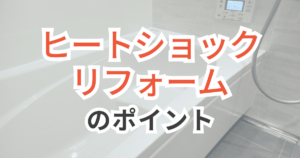
ヒートショック予防・対策にはリフォームがおすすめ!補助金や注意点も解説!
ヒートショックとは急激な温度差から起こる症状であり、高齢者の事故などをニュースでご覧になった方も多いと思われます。本記事ではヒートショックの予防や対策を行うために、症状が発生する基礎知識やリフォーム方法に関して詳しく解説していきます。
ヒートショックとは急激な温度差から起こる症状であり、高齢者の事故などをニュースでご覧になった方も多いと思われます。本記事ではヒートショックの予防や対策を行うために、症状が発生する基礎知識やリフォーム方法に関して詳しく解説していきます。
市区町村を選ぶだけ
市区町村を選ぶだけ
実家のリフォームで利用できる補助金制度

実家のリフォームをしたいけどお金がないときは、以下の補助金制度を活用しましょう。
- 介護保険による住宅改修
- 次世代省エネ建材支援事業
- 長期優良住宅化リフォーム
以下で、それぞれの補助金制度について説明します。
介護保険による住宅改修
介護保険による住宅改修は、要支援又は要介護の認定を受けている人が住んでいる住宅を対象に、バリアフリーリフォームの自己負担を軽減するための補助制度です。
介護保険が適用されるリフォーム内容は下記の通りです。
- 手すりの取り付け
- 段差の解消(バリアフリー)
- 床材の張替え(転倒防止床材のみ)
- 扉の改修(引き戸など)
- トイレ改修
- 風呂場改修
- 階段用リフト設置
- 玄関スロープ設置
- 玄関灯・足元灯
介護保険による住宅改修の支給額は20万円を上限として、実際にリフォームにかかった費用の1~3割が自己負担となります。つまり、住宅改修工事に20万円かかった場合、自己負担額(2~6万円)を差し引いた残りの金額が介護保険から支給されます。
介護保険を利用した住宅改修は、基本的に1人1回のみの利用に限られています。複数回にわけてバリアフリーリフォームを行ったとしても、介護保険の支給対象となるのは原則1回のみです。
ただし、3段階以上の要介護度が上昇した場合や、別の家に転居したことで再度バリアフリー化が必要と認められると、再度住宅改修の利用ができるケースもあります。
次世代省エネ建材支援事業
次世代省エネ建材支援事業は、省エネリフォームを促進し、次世代省エネ建材の効果の実証を支援するための補助金・補助制度です。
経済産業省が行っており、既存の住宅に工期を短縮できる高性能断熱材や、快適性の向上が期待できる蓄熱・調湿材などの次世代省エネ建材を用いてリフォームを行う場合に補助金が交付されます。
対象は外張り断熱工法や内張り断熱工法等での改修で、補助金が使える工事と補助額については区分されています。戸建て住宅で最大400万円の補助金を受け取れます。
毎年、公募期間が設定されており、予算に達すると公募期間中でも申請を締め切ることがあるため、注意しましょう。
参考:令和4年度 次世代省エネ建材の実証支援事業 | 一般社団法人 環境共創イニシアチブ
長期優良住宅化リフォーム
「長期優良住宅化リフォーム」とは、既存住宅を長期的に維持管理し、将来的にも住み続けることができるよう、性能向上を図るリフォームです。
このリフォームには、耐震性や省エネ性などに優れた住宅ストックを形成するための特例措置があり、補助金制度の他に所得税の特別控除が設けられています。
長期優良住宅化リフォーム推進事業は、一定の性能基準を満たすリフォームに工事を行う住宅所有者に対し、リフォーム工事費の1/3以内かつ、戸あたり上限100万円の補助金を支給する制度です。
ただし、事業者登録や住宅登録などの手続きが必要であり、要件を満たす必要があります。適用期限があるので、詳細は必ず確認しましょう。
参考:長期優良住宅化リフォーム推進事業 | 国立研究開発法人 建築研究所
市区町村を選ぶだけ
市区町村を選ぶだけ
実家のリフォームで活用できる減税制度
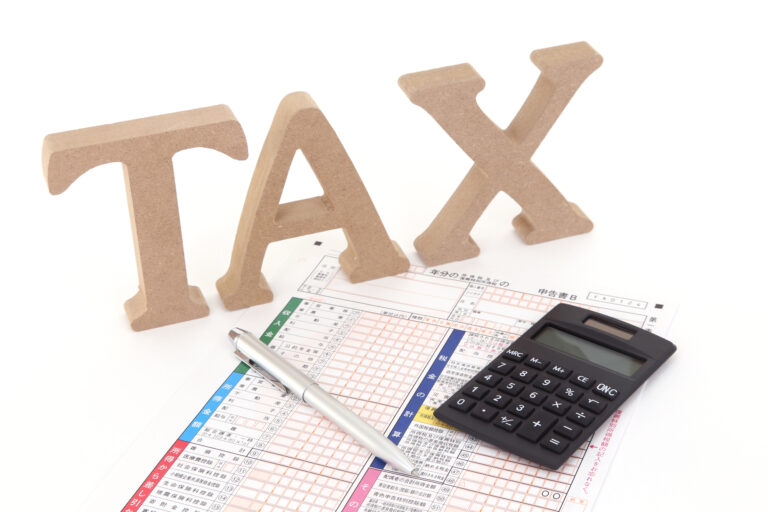
実家のリフォームでは、補助金の他にも以下のような減税制度を活用できます。
- 住宅ローン減税(住宅ローン控除)
- 耐震改修に関する特例措置
- 同居対応改修に関する特例措置
本章では、実家のリフォームにおける減税制度について詳しく解説します。
住宅ローン減税(住宅ローン控除)
住宅ローン減税は、返済期間が10年以上にわたる住宅ローンを借り入れて、住宅の新築・取得または増改築などをした場合に税控除が受けられる制度です。住宅ローンを借りて増築・改修などのリフォームを行った場合も本制度の対象となります。
控除される金額は年末時点のローン残高の0.7%です。所得税(一部、翌年の住民税)から控除されます。他の減税制度よりも適用期間が長いことが特徴であり、既存住宅のリフォームの場合は10年間利用できます。
ただし、リフォームで住宅ローン減税を受けるには、建築基準法に規定する大規模な修繕や一定のバリアフリー化・省エネ化工事を行うなど、工事の内容や費用にいくつか条件があります。
住宅ローン減税の内容は毎年少しづつ変更になることも多いため、国土交通省や国税庁の最新情報を確認しておくとよいでしょう。
耐震改修に関する特例措置
耐震改修に関する特例措置は、現在の耐震基準を満たさない住宅を耐震リフォームした場合に対象となる減税制度です。
旧耐震基準(昭和56年5月31日以前)により建築された住宅を現行の耐震基準に適合させるリフォームが対象であり、耐震改修パネルの増設や土台の補強などが該当します。
減税額は標準的な工事費用相当額の5~10%であり、所得税から控除されます。
また、工事完了日から3か月以内に市区町村窓口に所定の書類を提出することで、翌年度の固定資産税が2分の1に減額されます。
同居対応改修に関する特例措置
同居対応改修に関する特例措置は、多世帯住宅を開始するための設備増設や、それらと同時に増改築工事を行った場合に対象となる減税制度です。
増設する設備はミニキッチンやシャワーのみの浴室でも減税の対象となりますが、その場合はミニキッチンでないキッチンや浴槽のある浴室をリフォーム改修後に備えている必要があります。
減税額は標準的な工事費用相当額の10%+控除対象限度額を超える部分(または増築・改築などの一定工事に要した費用)の5%であり、所得税から控除されます。
ただし、前述の「住宅ローン減税」との併用はできないので注意が必要です。
なお、ここで挙げた減税制度は「減税を受ける本人が居住している住宅」であることを要件としています。
そのため、ご自身が住む予定のない実家をリフォームする場合には、対象外となる可能性があることを覚えておきましょう。
市区町村を選ぶだけ
市区町村を選ぶだけ
実家をリフォームする際は贈与税に注意

実家をリフォームする際には、贈与税に注意する必要があります。
贈与税は、相手方に財産を無償で譲渡した場合に課税される税金であり、実家をリフォームする際に、贈与税がかかるケースがあるからです。
例えば、親が名義人である実家を子供がリフォームする場合、子供が負担する費用が一定金額を超えると、贈与税がかかる可能性があります。
贈与税を回避する方法としては、子が実家を購入して名義変更する方法と、親が子に実家を贈与する2つの方法があるので、どちらかの方法を活用してみてください。
市区町村を選ぶだけ
市区町村を選ぶだけ
補助金や減税制度を利用してお得に実家をリフォームしよう

本記事では、実家をリフォームするにあたっての費用相場や費用を抑える方法について解説してきました。
実家をリフォームする目的には「安全性や快適性の向上」「二世帯住宅への改装」「家の継承・貸し出しのための価値向上」があります。建て替えかリフォームかで迷った際には、今後も長く住み続けるかを軸に考えると良いでしょう。
実家をリフォームするにあたり、「バリアフリー化」「断熱・耐震」「内装」「間取り変更」といったさまざま種類があるので、自分の実家に必要なリフォームを見つけましょう。
また、金銭的に余裕がない場合は、補助金や減税制度を活用しましょう。制度について分からないことがあれば、まずは専門家に相談することもおすすめです。