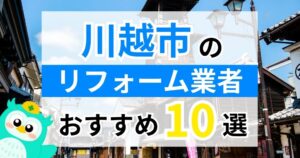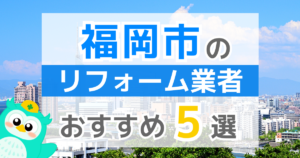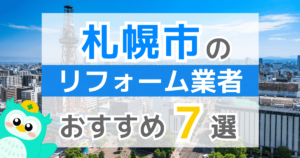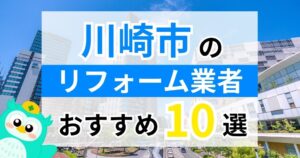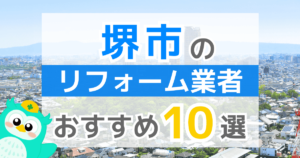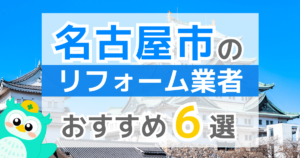リフォームする箇所を選ぶ
三世帯住宅の間取りは何がおすすめ?三世帯にするメリット・デメリットもご紹介

現代の住宅事情において、三世帯住宅が注目されています。3世帯が1つの家に住むことで、家族の絆を深めるだけでなく、生活費用や介護負担を分散させることができるというメリットがあるからです。
本記事では、三世帯住宅のメリット・デメリットや間取りなどを詳しく解説していきます。
【関連記事】
>>リフォームの費用相場
市区町村を選ぶだけ
市区町村を選ぶだけ
目次
三世帯住宅とは?

三世帯住宅とは、3つの世帯が1つの建物で一緒に暮らす住宅のことを意味します。この場合は「親世帯+子世帯+孫世帯」「親世帯+子世帯+子世帯」「親世帯+親世帯+子世帯」などがさまざまな家族の組み合わせがあります。
多世代で同じ建物内に住むことで互いに支え合い、助け合いの生活が実現可能になります。三世帯住宅は高齢化が進む日本で多世代が共に暮らすことのメリットを享受できる住宅スタイルとして、近年注目されています。
市区町村を選ぶだけ
市区町村を選ぶだけ
三世帯住宅の主な家族構成パターン

三世帯住宅における主な家族構成パターンは、さまざまな組み合わせが存在します。それぞれの世帯がどのように関係し、どのような生活を送るのかを把握することが重要です。
以下では、三世帯住宅でよく見られる家族構成パターンを3つ紹介します。それぞれのパターンの特徴と適した住宅形態を理解しましょう。
①親世帯+子世帯+孫世帯(もしくは祖父母世帯)
家族構成の1つめは、親世帯+子世帯+孫世帯(または祖父母世帯)が一緒に暮らす形です。この構成では、家族全員が協力し合い、子育てや高齢者の介護をサポートできます。
また、家族間のコミュニケーションが密であり、親子・祖父母と孫の関係が深まりやすいのが特徴です。
②親世帯+子世帯(兄姉夫婦)+子世帯(弟妹夫婦世帯)
家族構成の2つ目は、親世帯+子世帯(兄姉夫婦)+子世帯(弟妹夫婦世帯)が一緒に住むパターンです。この構成では、兄弟家族が連携して家計や子育て、介護をサポートし合います。
さらに、兄弟間の親睦が深まり、家族全員で助け合うことが可能となる魅力があります。
③親世帯(夫婦の両親)+子世帯
家族構成その3は、親世帯(夫婦の両親)+子世帯が同居する形態です。ここでは、子世帯が両親の世話を行いつつ、祖父母世代からも子育てや家事のサポートが受けられます。
この構成は、家族間の助け合いが強化されるだけでなく、夫婦両親とのつながりも維持されるという利点があります。
市区町村を選ぶだけ
市区町村を選ぶだけ
三世帯住宅のメリット

三世帯住宅のメリットは、住宅費用が抑えられる、家族間での育児・介護支援、家事の分担による生活効率化、そして相続税の減税が挙げられます。詳細を確認していきましょう。
①住宅購入や建設費用が抑えられる
三世帯住宅のメリットの1つとして、住宅購入や建設費用が抑えられることが挙げられます。通常、それぞれの世帯が別々の住宅を購入・建設する場合、その費用はかなり高額になります。
しかし、三世帯住宅を検討することで、家族全員が一つの住宅に暮らすことにより、総費用が削減できます。
また、家族全員が共同で住宅購入や建設に関わることで、各世帯が個別に抱える負担も軽減されることになります。これにより、家族それぞれが資金面で余裕を持ち、より良い生活環境の実現が可能となります。
さらに、三世帯住宅では、共有スペースを設けることで、建物自体の有効活用が期待できます。リビングやキッチン、浴室などを共有することで、それぞれの世帯が個別に設けるよりもスペース効率が向上し、建築費用を削減できる場合があります。
②育児や介護など家族の支え合いができる
メリットの2つ目は、三世帯住宅では育児や介護など、家族が互いに支え合うことができます。親世帯と子世帯が一緒に暮らすことで子どもの世話や教育において親世代がサポートでき、子世代の育児負担が軽減されます。
また、子どもたちにとって祖父母とのふれあいが増えることで、家族の絆が深まります。
一方、高齢化社会が進む中で、介護が必要となる親世代のケアも重要な課題となっています。三世帯住宅では、子世代や孫世代が近くにいることで、介護や緊急時の対応が迅速に行え、安心感が得られます。
加えて、家族間で介護の負担を分散させることができるため、それぞれの世帯が適切なバランスで支援を行うことが可能です。
三世帯住宅では家族が互いに助け合いながら、育児や介護といったライフイベントに対応できる環境が整うのです。家族全員が安心して暮らすことが実現できます。
③家事などの分担ができ生活が効率化
メリットの3つ目は、三世帯住宅では家事などの分担ができ、生活が効率化されることです。
三世帯住宅では、家族全員が協力して家事や炊事、買い物などの日常業務をこなせるようになります。各世帯が個別に家事を行うよりも時間や労力を節約できるのです。
例えば、食事の準備や片付けをローテーションで行うことで、それぞれの世帯が自由な時間を確保できるようになります。また、買い物や家事のスケジュールを共有し、効率的に分担することで、無駄な買い物や作業の重複をなくします。
さらに、家族間でスキルや知識を共有し、互いに学び合うことができる環境が整います。家事能力が向上し、生活のクオリティも高まることが期待できるでしょう。
三世帯住宅では家族全員が協力し合い、家事を分担することで効率的な生活を送れる魅力があります。
④相続税の減税
三世帯住宅では相続税の減税が受けられる可能性があります。相続税は、一定額を超える遺産を相続する際にかかる税金で、その額は遺産の価値に応じて変動します。
しかし、三世帯住宅を建設・購入する場合、一定の条件を満たすことで、相続税の減税措置を受けることができます。
三世帯住宅を相続する際には、住宅の一部が「特別居住用財産」として評価されることがあります。通常の住宅に比べて低い評価額で計算され、相続税の負担を軽減できるのです。
減税措置は、家族が同居または近居し、世代間での支え合いを促進することを目的として導入されています。
三世帯住宅を検討する際には、この相続税の減税が適用される条件を確認し、適切な計画を立てることが重要です。家族全員が安心して暮らすだけでなく、経済的なメリット享受も期待できます。
市区町村を選ぶだけ
市区町村を選ぶだけ
三世帯住宅のデメリット

三世帯住宅には、プライバシーが保たれない可能性や、一世帯分が空いてしまうリスクがあります。メリットに限らずデメリットも考慮して家族と十分に話し合い、適切な設計やルール作りが重要です。詳細を確認していきましょう。
①プライバシーが保たれない可能性
三世帯住宅ではプライバシーが保たれない可能性があります。家族が1つの建物に住むことで自然と家族間の距離が縮まりますが、逆にプライバシーの侵害につながることがあります。
例えば、家族間での騒音や臭いの影響が及ぶことがあったり、互いの生活リズムや価値観の違いが生じる場合もあります。解決策としては、間取りや設計段階でプライバシーを確保する工夫が必要です。
例えば、各世帯のリビングや寝室を離すことで、騒音の伝わりを抑えたり、共用部分と個別の空間を明確に区切ることで、家族間の距離感を適切に保つことができます。
また、家族でルールを共有し、互いのプライバシーを尊重することも大切です。お互いに扉をノックしてから入ったり、共用部分での騒音を避ける時間帯を設定したりしましょう。
最低限のマナーに配慮をすることで、三世帯住宅でも快適な生活を送れるようになります。
②一世帯分が空いてしまう可能性
三世帯住宅のデメリットの2つ目として、一世帯分のスペースが空いてしまう可能性が挙げられます。
子どもが独立したり、親世帯が亡くなったりした場合、家の中に余剰なスペースが生じる可能性が考えられるからです。このような状況では、維持費や管理費が無駄にかかることになり、経済的な負担が増すことが懸念されます。
空いたスペースを有効活用するためには、柔軟な間取りや設計が重要です。
例えば、将来的には賃貸物件として利用できるよう、独立した入り口を設けること。余分なスペースを趣味や仕事の場として活用できるようにすることなどが考えられます。
また、将来的な家族構成の変化を見据えて、建物を増改築しやすい設計にすることも有効です。家族の状況に合わせて最適な住まいに柔軟に変更することができます。
空いたスペースに対処するためには、家族の将来のプランを話し合い、適切な設計や間取りを検討することが大切です。
市区町村を選ぶだけ
市区町村を選ぶだけ
三世帯住宅の間取りは3種類

三世帯住宅の間取りには、完全分離型、部分共有型、完全同居型の3種類があります。家族のニーズやライフスタイルに合わせて、最適な間取りを選ぶことが快適な暮らしにつながります。それぞれ詳細を確認していきましょう。
プライバシーの確保を最優先【完全分離型】
プライバシーの確保を最優先する場合は、完全分離型の三世帯住宅がおすすめです。完全分離型の住宅は各世帯が独立した空間を持ち、共用部分が最小限に抑えられているからです。
家族間での騒音や生活リズムの違いが影響しづらく、プライバシーが保たれやすい魅力があります。
また完全分離型の住宅では、それぞれの世帯専用の入り口やリビング、キッチン、浴室などが設けられており、まるで別々の家に住んでいるかのような環境が実現されます。家族同士の距離感が適切に保たれるため、ストレス軽減につながるでしょう。
ただし、完全分離型は共用部分が少なく、家族との助け合いやコミュニケーションが難しくなることがあります。事前に、家族間のコミュニケーション方法や緊急時の対応などを話し合っておくことが重要です。
ルールを決められるなら【部分共有型】
部分共有型の三世帯住宅は、一部の空間を共用しながらも、各世帯が独立したプライベート空間を保てます。
例えば、リビングやキッチンは共有しながら、寝室や浴室を各世帯ごとに設けることで、プライバシーと家族のつながりを両立できます。
また部分共有型の住宅では、家族間のコミュニケーションや助け合いもしやすいため、育児や介護などの支え合いが容易になります。
ただし、共有空間の利用ルールや騒音対策などを家族で話し合い、明確にしておくことが大切です。
さらに、共有部分の有効活用は家事の分担や費用面でも効率化が図れます。家族が集まる共有空間では、親子や兄弟間の絆を深める機会も増えるでしょう。
部分共有型は、家族のニーズや価値観を尊重し、適切なルールを設けることで快適な暮らしを実現できます。
費用を抑えるなら【完全同居型】
完全同居型の三世帯住宅は、全ての空間を共用しながら、建設費や光熱費を抑えられる間取りのことです。キッチンやリビング、寝室、浴室などを家族全員で共有するため、建物自体の規模が小さくなり、初期費用や維持費を削減できます。
しかし、完全同居型の住宅では、プライバシーが十分に保たれないことがデメリットです。そのため、家族間のコミュニケーションやルール作りが特に重要となります。
また、家族構成やライフスタイルの変化に対応できる設計が求められます。完全同居型の住宅では、家族間の助け合いやコミュニケーションが生活の中で自然に生まれやすく、家族の絆を強めることができます。
ただし、家族の価値観やライフスタイルが大きく異なる場合は、ストレスを感じることもあるため、十分な話し合いや検討が必要です。
費用を抑えたいというニーズが強い場合は、完全同居型を検討することで、効率的な生活が実現できます。
市区町村を選ぶだけ
市区町村を選ぶだけ
まとめ

三世帯住宅を実現するためには、家族構成や暮らし方に合わせた間取りを選び、費用や補助金の活用方法も把握する必要があります。
また、プライバシーや生活習慣の違いについても考慮し、ルールを決めることが大切です。
さらに、リフォームの際には専門家の意見を参考にし、安全性や快適性に配慮したリフォームを行うのが望ましいといえます。
三世帯住宅は、家族が支え合いながら暮らすことができる暮らし方です。慎重な計画と準備をして快適な空間づくりを実現しましょう。